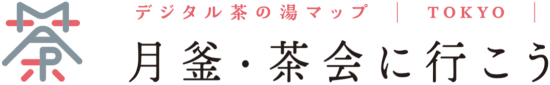
大学生による体験レポート
ギャラリー Hechiさん
文・立教大学茶道部 佐藤功一

東京都狛江市岩戸のギャラリーhechiさんにて、インタビューを行いました。
成城学園から一駅先、小田急線の喜多見駅から徒歩4分。穏やかな住宅街に一つ、スタイリッシュで目に留まる佇まいのお店がございます。そこで店主の清水様にお話を伺いました。
「hechi」というお名前は、伝承に残る茶人「丿貫(へちかん)」の名前に由来します。丿貫は、お湯を沸かすための手取釜で毎日雑炊を作る、風変わりな茶人として知られていました。千利休とも交流があり、茶席で利休を敢えて落とし穴に入れ、身を清めた上でお茶を振る舞ったという逸話が残っております。常識に捉われず、オリジナリティを貫いた茶道具を作りたい思いから、丿貫より「丿」の字をお借りしたとのことです。

そんなギャラリーhechiの十八番は、「ヤン・リーパオ」を用いたオリジナルの茶道具です。耳慣れない「ヤン・リーパオ」というのは、タイ南部の熱帯雨林に自生するツル植物の名前、およびそれを素材とした工芸品の名前とのことです。(詳しくはギャラリーhechiのHPに記載されています)
hechi iのオーナーが数十年も前にメトロポリタン美術館で目にしたヤン・リーパオが忘れられず(その時は何の素材か分からず、馬の毛かとも思ったそうです。)、そこから数十年の時を経て国内外の様々なご縁が繋がり、オリジナルのヤン・リーパオ製品が作れるようになり…、現在に至るそうです。
道具のデザインは、ギャラリーhechiオリジナルのものになっています。国内外の職人の方と打ち合わせながら、専門の異なる作家の手から手に渡って加工され、場合よっては数ヶ月の長い時を経て、茶道具としての工芸品が出来上がります。
茶道もその昔中国から伝来したように、海外から取り込み日本で育てられた文化は数多くあります。ヤン・リーパオは収穫量・技術者ともに減少しており、希少な素材となっていますが、東南アジアの優れた文化が日本に溶け込んでくれたら嬉しい、そのような思いからお道具作りに注力されています。ヤンリーパオ製品だけでなく、そのほか現地の織物や染物を使った着物や帯・数奇屋袋など、さらなる文化の融合も試みられております。

またhechi様は、茶道具のあり方自体にも新しい風を吹かせようとしています。例えば、小さな板を蛇腹に曲げて連ねた、持ち運びの効く結界は、下部にある三日月型の窪まりと叉木を組んで安定させることができます。また、近年は炭を使う機会が減っているため、敢えてコードの通り道を作り、IHや電熱器に対応した土風炉を作るなど、伝統と現代の融合にも取り組まれています。さらには、先の織物を使ったトートバッグなど、茶道具に限らず日常に寄り添った道具作りにも熱心です。
他にも様々なお道具が展示されていましたが、全てを紹介することはできませんでした。マニアックな茶器から斬新なアイデアまで、どれも「物語」を秘めており、その背景を伺うことで新たな発想や景色に触れる、とても貴重で楽しい経験をさせて頂きました。
店主の清水さんは、「このギャラリーに色々な人が来て、お話が出来る集い場になると嬉しい」とおっしゃっていました。みなさんもぜひ、新たなあなたに会うために、一度足を運んでみてはいかがでしょうか。
ギャラリーhechiの清水様、貴重なお話と取材へのご協力をいただき、ありがとうございました。
| 所在地 | 東京都狛江市岩戸北2-16-11 |
| TEL | 03-6751-2127 |
| 営業時間 | 10:00~17:00 不定休 |
| アクセス | 小田急線「喜多見」駅から徒歩4分 駐車場もございます。 ※お車でご来店予定の方はお手数ですがご一報いただけますとスムースです。 |