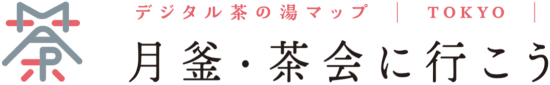
田野倉建築事務所
たのくらけんちくじむしょ

田野倉建築事務所の代表・田野倉徹也さんは、茶室や数寄屋造りの住宅、社寺、舞台など日本建築を専門に手がける数寄屋建築家です。2015年(平成27)3月に六本木ヒルズアリーナで初公演が行われた「にっぽん文楽」プロジェクトでは、一日で組み立てる檜舞台が話題をよびました。これも田野倉さんの作品です。この祝祭の仮設舞台はその後、大阪、浅草、難波、伊勢、上野、熊本と各地を巡業し、2019年3月に明治神宮にお目見えしました。
大学で建築を学んでいるころから最先端のガラスとコンクリートの現代建築に興味が持てず、古い木造建築にひかれていた田野倉さんは、指導教授のすすめで茶室の研究に没頭しました。大学院修了後、鹿島建設設計部に就職するも、やはり数寄屋がやりたくて退社して独立。そのきっかけは漫画家の山下和美さんとの出会いでした。
若き建築家「蔵田徹也」との交流から、もともと自分の中にあった「和」への憧れに目覚めた女漫画家は、数寄屋造りの自宅を新築する決意を固めます。『数寄です!』(全3巻・続2巻/集英社)は、そこから始まった土地選びから竣工に至る、2年間のてんやわんやの日々を描いたエッセイコミックです。この建築家のモデルが田野倉さん。監修とコラム執筆も担当しており、漫画を楽しみながら数寄屋やお茶、家にまつわる日常の作法など日本の伝統文化に詳しくなれるという、入門書のような趣もある作品です。
現代の数寄屋に「木の家は寒い」「瓦屋根は地震に弱い」といった過去のマイナスイメージは当てはまりません。最新のテクノロジーを取り入れ、それまでの生活スタイルを変えることなく暮らせます。数寄屋の魅力について田野倉さんは、「居心地がよくて暮らしやすく、長持ちする。そして、美しい。それが数寄屋だと思います」と語ります。材木や瓦などの材料を選ぶため、施主と一緒に生産地の職人を訪ねるのも、田野倉さんが大切にしていることの一つです。失われつつある日本の自然や伝統技術とつながっている家。そこでの暮らしには、日本文化に仲間入りできた喜びがあるに違いありません。
山下和美邸


隣接するお寺の緑を借景し、仕事場に籠りがちな生活の中で 、四季 が 感じ ら れ る 回遊できる造り と な ってい る 。
にっぽん文楽組立舞台


土台・柱梁・足脚の軸組と壁・屋根パネルで構成され 、 20 人 の 宮大工 が 約 1 日 で 組 立てが可能なように作られている。
www.nipponbunraku.com/archive/
岩惣洗心亭


昭和の文豪が逗留した昭和24年築の離れを、茶室仕様の客室として改築。既存床は書院床とし、新たに表玄関と床の間を設けた。
www.iwaso.com
RSKイノベイティブ・メディアセンター内 能楽堂ホール tenjin9


放送局内につくられた能舞台。「桃太郎伝説の生まれたまち 」に相応しい古代の神社を想像させる姿。2020年10月、こけら落とし公演が催された。
tenjin9rsk.jp

慶圓寺本堂(葛飾区新宿)

大福寺門徒会館(雲仙市古城名)

江島神社奉安殿(藤沢市江の島)
enoshimajinja.or.jp

小山田邸修楽亭(奈良市柳生町)

鮨海界(港区六本木)
www.sushikaikai.com

オカモトヤ文具店(港区虎ノ門)
www.okamotoya.com

世田谷区豪徳寺にある木造洋館「旧尾崎テオドラ邸」は1888年(明治21)港区に建てられ、1933年(昭和8)に現在地に移築されました。一時、解体の危機にありましたが、漫画家・山下和美さんが中心となった保存活動が実り、現在は一般社団法人旧尾崎邸保存プロジェクトが所有しています。田野倉さんも当初から山下さんとともに保存活動に取り組んできました。詳しい経緯は山下和美さんのコミックエッセイ『世田谷イチ古い洋館の家主になる』(全3巻/集英社)をご覧ください。

階段
田野倉さんの指揮のもと10カ月に及んだ修復作業を経て、「旧尾崎テオドラ邸」は建築当時の姿を取り戻しました。2024年(令和6)2月、1階にカフェとショップ、2階にギャラリースペース(写真)を設けた文化施設としてグランドオープンします。「旧尾崎テオドラ邸は、現代ではもう造れない貴重な建物です。ここではタイムマシンのように時間をさかのぼることができますよ。ぜひお訪ねください」(田野倉さん)。
チャゲさんとのトークショーも!
修復が完了した2023年の11月下旬、保存活動を応援してきた歌手のChageさんの呼びかけで、ファンクラブによる見学会+支援ミニライブが開かれました。田野倉さんとのトークショーもあり、Chageさんの軽妙な語り口に会場は大いに盛り上がりました。
『五十八さんの数寄屋』

建築家・藤森照信さんと田野倉さんの共著『五十八さんの数寄屋』(鹿島出版会)。数寄屋の近代化に込めた吉田五十八の建築思想と、その作品について深く知りたい方におすすめです。巻末にはお二人の対談も収録されています。
www.amazon.co.jp/dp/430604677X
『はな、茶の湯に出会う』

はなさんを護国寺に案内する一コマ『はな、茶の湯に出会う』(淡交社)。淡交カルチャー教室の「数寄屋建築家と歩く茶室散歩」の他、新宿柿傳の茶の湯同好会でも、数寄屋の講義や見学会を行っている。
www.cha-no-yu.jp
| 住所 | 東京都世田谷区豪徳寺2丁目30−16 |
| FAX | 03-4333-0825 |
| info@tanokura.jp |