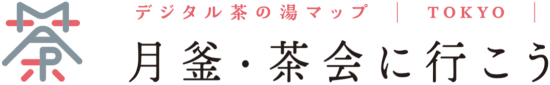
有限会社サンアイ
ゆうげんがいしゃさんあい

炭を使わず電気で湯を沸かせる茶道用電熱炉は、その便利さと安全性から広く愛用されています。電熱器は陶製で炭の形を模しており、通電するとあたかも炭が熾っているように見えるところも、茶道に親しむ人たちの支持を得た理由のひとつといえるかもしれません。
茶道用電熱炉には、床下に埋め込む炉壇、床下が取れない部屋で使える置炉、そして風炉があります。構造も、使われている材料もそれぞれ異なり、設計段階から組立作業まで、高い技術力が求められます。創巧野々田の社長が発明したことから「野々田式」と呼ばれこの茶道用電熱炉の製造を長年にわたり担ってきたのが、昭和54年(1979)に創業した電機・機械メーカー「サンアイ」です。創業者の山上博愛さんは、家電メーカーの機械設計技術者だったときに創巧野々田の社長と知り合いました。茶道用電熱炉の設計・製造を柱にすえて30代で独立すると、納骨堂の増加を見越した納骨壇用電気香炉、無人の墓地でも安全に使える寺院・霊園用線香着火器など、従来の使い方を踏まえつつ電気で便利で安全に使えるオリジナル製品を開発してきました。
平成30年(2018)に創巧野々田が廃業したため、サンアイは茶道用電熱炉事業を引き継ぐ形になりました。顧客のさまざまな注文にきめ細かく対応できる少数精鋭の社員の技術力を強みに、2代目の博道さんは、今後はさらに企画力を発揮して、電熱炉の可能性をさぐっていきたいと話します。「たとえばお祭りのイベントに野点を提案したり、置くだけでその一角が茶室になる立礼卓を広めるなど、電熱炉の製造を通して茶道の普及に貢献できればいいなと考えています」。
炭型電熱器を陶器にセットした風炉各種。いずれも香入、まえかわらけ、敷板付き。


左は「信楽 紅鉢」(径29.5㎝・高さ18.5㎝)、右は「白さつま」(径28.5㎝・高さ18㎝)


左は「びわ色さつま」(径28.5㎝・高さ18㎝)、右は「黒 紅鉢」(径28.5㎝・高さ17.5㎝)

「真塗 紅鉢」(径30㎝・高さ19㎝)。


炭型電熱器をセットした置炉は、炉壇を設置できない部屋におすすめです。
材は高級感のある女桑(左)と焼杉(右)の2種類。


炉壇には通常の和室用と床下が十分にとれない場合のビル・マンション用があり、取り付け用下地の炉壇うけ(別売)と炉縁(別売)の3点ユニットになっています。畳の表面にコードを見せずにセットでき、操作も簡単な4段切替スイッチ付き。

セラミックヒーターを使用することで、裸火が使用できない室内での焼香を可能にした納骨壇用電気香炉。東京の増上寺、京都の大谷本廟などで使われています。右から青磁浮絵香炉、青磁玉香炉、机上香炉。

線香着火器「線香当番」はニクロム線を使用しています。

山上博愛さん(右)と博道さん。本社応接室にて。

茶道教室でお点前の練習に臨む博道さん。もっと茶道について学び、視野を広げたいと2年前から通い始めました。

裏千家正教授で埼玉県茶道連盟副理事長を務める小野宗孝先生が埼玉県川口市の自宅で開いている教室には、近所の小学生からお茶の先生まで年齢も経験もさまざまな生徒さんたちが通っています。初心者クラスの指導は小野宗佳先生が担当しています。

稽古では道安風炉面取(小)が使われました。水指はオランダで買い求めたデルフト焼。

サンアイの本社と工場は越谷市にあります。小売りはしていませんが、製品に関することはお気軽にお問い合わせください。
*サンアイの電熱炉は、有名デパート、全国茶道具店、茶舗・花器店でお求めいただけます。
*サンアイの電熱炉は淡交社物販営業部でもお求めいただけます。下記へご連絡ください。
TEL 075-432-5151(平日9:00〜17:00) FAX 0120-310-278(24時間受付)
*電熱炉はじめサンアイ製品の仕様などに関するお問い合わせは下記へ。
| 住所 | 埼玉県越谷市東大沢3-1-11 |
| TEL | 048-976-0321 |
| FAX | 048-976-0332 |
| info@sanai-tech.co.jp |