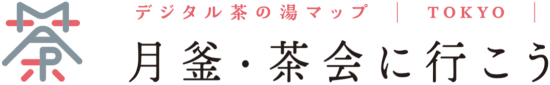
森の恵
もりのめぐみ
数寄屋建築を得意とし、ライフスタイルにあった茶室づくりを提案する工務店・森の恵。昭和30年(1955)に創業されました。茶室づくりは、二代目の現社長である父の松永賢司さんが始めました。賢司さんは知識を得るために習い始めた茶道に魅せられ、茶人として自身の稽古場を持つまでになりました。賢司さんの手掛ける茶室は、大工としての技だけでなく、茶人として施主と同じ目線で、生活にも馴染みつつ使い勝手が良いと評判で、その実績を年々増やしています。3代目の泰輔さんも、裏千家学園に学び茶道の世界に身を置いて、大工である弟とともに、家族で茶の湯を楽しみながら、工務店・森の恵の次代として、茶室づくりを提案していこうとしています。

設計・施工した茶室「木乃き庵」。由緒ある古材が高度な大工の技で生かされています。取り込む光の陰影によって厳かな雰囲気に。

森の恵が設計施工した水屋。たくさんの光が取り込まれて美しく、床下を生かした大容量の収納も確保しています。森の恵が提案する茶室は、マンションでも戸建のリフォームでも、見事に水屋も含めた動線が確保され、フレキシブルに空間を生かして、適切に設計されています。

オリジナルの立礼棚。

鎌倉の「一条恵観山荘」に納品した、茶室で使える腰掛け椅子。2つを入れ子式に組み合わせて収納できます。こうした目的に即した便利なプロダクトも製作しています。

施工例「葉葉庵茶室」
ツーバイフォー工法で建てられた住宅の八畳洋間を京間四畳半の茶室に改修。周囲が開けた風通しのよい立地の魅力を生かすため、南側に色紙窓、西側に書院窓を設けました。とても明るい茶室ですが、お点前の場には光が入らないよう工夫されています。

水屋から茶室を見る。水屋は階段下を有効利用しました。収納棚を取り付けた部分は増築です。


茶室外観と露地。外壁は藁入りリシン吹き付け仕上げです。塀は南側(正面)は杉皮、西側は青檜葉を用いています。

施工例「磯村邸陽明菴」
平地を掘り下げた半地下のホビールームを京間八畳の広間に改修。京都・唐長の唐紙が空間を上品に引き締めています。


庭の緑とつくばいが望める半円形の下地窓、露地から差し込む光をやわらかく受け止める、入り側の障子窓と茶室の障子戸の重なり。得てして堅苦しくなりがちな広間をなごやかな空気で満たす窓の演出です。


施工例「M邸」
広いリビングの一角に設けた、オーソドックスな様式の四畳半の茶室。赤松の網代天井がぬくもりを添えています。隣接する洋間の掃き出し窓越しに露地が見えます。
| 所在地 | 横浜市栄区桂町325-1パセアル本郷台102 |
| TEL | 045-890-1213 |
| TEL | 045-890-1214 |
| 営業時間 | 17:00~21:00 日曜・祝日休 |
| アクセス |
JR京浜東北・根岸線「本郷台駅」から徒歩15分 |