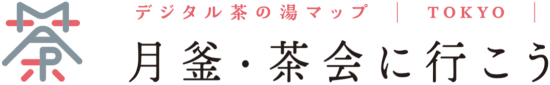
東京家政学院の課外授業

金井宗智先生は16年ほど前から、中高一貫の女子教育で知られる東京家政学院(千代田区三番町)で茶道の指導を続けています。「日本の文化と礼儀作法を身につけさせる」という学院の目標にしたがい、中学1年生から高校3年生を対象とした週2回の課外授業(選択科目)を受け持ち、また高校1年生(4クラス)の総合学習として年間8日間の授業も担当し、お客の作法や日本家屋での立ち居振る舞いなどを教えています。
22名の生徒が風炉の薄茶点前と盆略点前に分かれて稽古しました。薄茶点前の稽古は広間2間の隅に計4つの風炉を置き、亭主と客の2人セットで順番におこないました。

盆略点前の稽古は鞘の間(畳敷きの縁側)で。お手伝いに来てくれている東京家政学院の卒業生たちが指導しています。



東京家政学院の茶室は、茶道家・冠婚葬祭評論家として活躍した塩月弥栄子さん(1918〜2015)が同校専修科の講師を務めていた当時のもの。京都から運んだ材料を使い、裏千家営繕の職人が手掛けたと思われます。
北に本畳の床と貴人畳、南ににじり口、東と南に明かりを取った四畳半は裏千家今日庵の敷地内にある茶室「又隠(ゆういん)」の写し。これだけレベルの高い茶室が学校内にあるとは驚きです。

東京家政学院は2023年(令和5)に創立100周年を迎え、その記念に茶室の畳、襖、障子などを新装しました。24年(同6)4月10日には教職員を招いて新席披露茶会が開かれ、6年間宗智先生の授業を受けた卒業生たちが点前や半東、お運びを務めて接待しました。

「日本の伝統文化の中で、一生楽しめるものはお茶だと私は考えています。早くから茶道に親しむことが豊かな人生の基礎になります。このことを子どもたちに伝えていきたいですね」と宗智先生。正座もできなかった生徒がやがて点前ができるようになるなど、成長した姿を見るにつけ指導者冥利に尽きる喜びを実感するといいます。